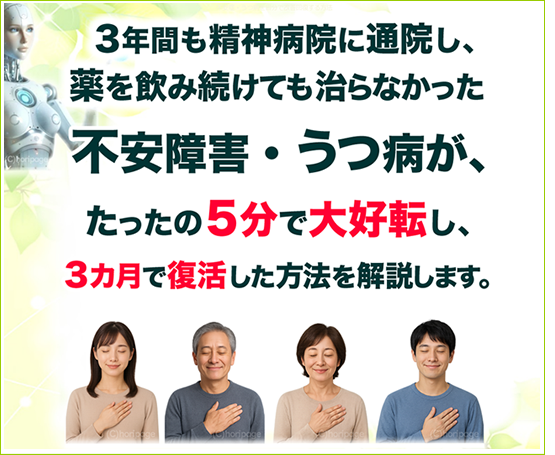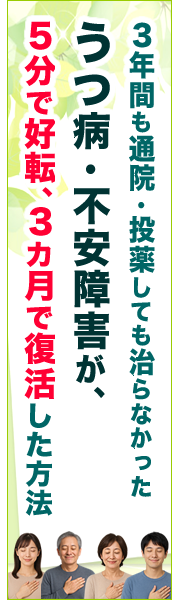うつ病に効く薬を飲みたくない場合・依存性が心配な場合など
うつ病の当事者は、何とか薬に頼りたくないという強い思いをもっていますが、支援者は、「先生の言うとおりしっかり飲むことが、うつ病回復の近道」ということを言い続けてください。
しかし、うつ病に効く薬を飲みたがらない人が多いのも事実です。そのときにはだましてでも飲ませるという手もあるでしょうが、一回ならともかく長く支援する支後者や家族にはそれも無理でしょう。
うつ病に効く薬を飲まない当事者の場合、支援者は、それでもいいと割り切るしかないでしょう。はたから見たらいばらの道でも、本人はそれしかできないのです。
もちろんその間も、うつ病に効く薬や治療に対する偏見を少しずつ解いていく努力は必要です。うつ病の波の調子のいいときを見計らって話をしてみてください。
一方、医師や看護師は、薬が身近にあり抵抗も少ないようです。その結果、うつ病の本質が疲労にあり休息をしなければならないのに、薬だけに頼ってしまう傾向があります。
疲れ果てている人に、栄養ドリンクを飲ませてそのときは元気が出たとしても、すぐにエネルギー切れするのは目に見えています。
医師や看護師の中には、薬で症状を抑えている間に、蓄積疲労をどんどんため、感情や行動をコントロールできず、周囲との関係をどんどん崩していってしまう人がいます。
うつ病に効く薬を飲みたくない場合・依存性が心配な場合
「うつ病かもしれない」と感じたとき、医師から抗うつ薬や睡眠薬をすすめられることがあります。
しかし、「薬に頼りたくない」「依存してしまいそうで怖い」と感じる方も少なくありません。
実際、薬を飲むことに抵抗を感じる人は多く、その気持ちは決して間違いではありません。
この記事では、うつ病の薬を飲みたくない場合にどうすればいいのか、また依存への不安をどう扱えばいいのかを、優しくわかりやすく解説します。
まず理解しておきたい「うつ病の薬」の役割
うつ病の薬(抗うつ薬・抗不安薬など)は、脳内の神経伝達物質のバランスを整えることで、気分の落ち込みや不安を軽くする効果があります。
たとえば、セロトニンという「幸せホルモン」が不足していると、気分が沈みやすくなったり、眠れなくなったりします。薬はこのセロトニンを増やし、脳の働きを元に戻すサポートをしてくれるのです。
つまり、薬は「心を変えるもの」ではなく、「脳の環境を整えるもの」。風邪で熱が出たときに解熱剤を飲むように、一時的なサポートとして利用するものなのです。
それでも、「できれば薬を使いたくない」と思う方がいるのも自然なことです。
その場合、いくつかの考え方と選択肢があります。
薬を飲みたくない理由を整理してみる
薬を避けたい気持ちには、人それぞれ理由があります。
-
副作用が怖い
-
依存してやめられなくなるのではと不安
-
「薬に頼るのは負けだ」と感じてしまう
-
自然に治したい
-
過去に薬でつらい経験をした
こうした感情を無理に押し殺す必要はありません。まずは、「自分はなぜ薬を飲みたくないと思っているのか?」を言葉にしてみることが大切です。
たとえば、ある40代の女性はこう話します。
「以前、睡眠薬を飲んでいた時期がありました。最初はよく眠れたけど、やめたら全然眠れなくなって...。また同じことになるのが怖いんです。」
このように「薬=怖いもの」という記憶があると、自然と抵抗感が生まれます。
その場合は、医師に「できるだけ薬を使わない方向で治療したい」と正直に伝えてみましょう。
医師によっては、心理療法や生活改善を中心としたアプローチを提案してくれることもあります。
依存性の心配はどう考えればいい?
「薬に依存してしまうのでは?」という不安は、多くの人が抱えています。
ここで知っておきたいのは、抗うつ薬と抗不安薬(安定剤)は性質が異なるという点です。
-
抗うつ薬(SSRIやSNRIなど) → 依存性はほとんどありません。
ただし、急にやめると離脱症状(めまい・不安感など)が出ることがあるため、医師の指導のもとで減らす必要があります。 -
抗不安薬(ベンゾジアゼピン系) → 長期間飲み続けると依存が起きることがあります。
ただし、短期間であれば安全に使える場合も多いです。
つまり、「依存が心配だから全部ダメ」というよりも、薬の種類と使い方の問題なのです。不安が強いときは、医師に「依存しにくい薬を選びたい」と伝えることもできます。
薬を使わずにうつを和らげる方法
薬を使わずにうつを改善するには、**「体」「心」「環境」**の3つを整えることがポイントです。
① 体を整える
うつ状態のときは、身体のリズムが乱れています。特に睡眠・食事・日光の3つが大切です。
-
朝起きたらカーテンを開けて光を浴びる
-
就寝前はスマホを避けて、ぬるめのお風呂にゆっくり入る
-
炭水化物を抜きすぎず、たんぱく質やビタミンB群を意識する
これだけでも脳内のセロトニンが増え、自然と気分が安定しやすくなります。
② 心を整える
うつ病の多くは、「自分を責める思考のクセ」が影響しています。たとえば、「こんな自分はダメだ」「もっと頑張らないと」といった自己否定の言葉です。
このクセをゆるめるために、認知行動療法(CBT)やマインドフルネスが役立ちます。
たとえば、毎晩「今日できたことを3つ書く」だけでも、脳の焦点が「できないこと」から「できたこと」に変わります。これは小さなようでいて、回復に大きく貢献します。
③ 環境を整える
うつ病は「ストレス環境」に長くいるほど悪化します。もし職場や家庭の環境がつらい場合、一時的に距離をとる勇気も必要です。
「逃げる=弱い」ではありません。たとえば、仕事を1か月休むことで、薬を使わずに回復した例も少なくありません。
環境を変えることは、「自分を守る力」を取り戻す行為なのです。
「薬を使わない」と「我慢する」は違う
ここで気をつけたいのは、「薬を飲まない=我慢する」ではないということです。
薬を使わない代わりに、他のケアをきちんと取り入れることが大切です。
たとえば、
-
カウンセリングや心理療法を受ける
-
栄養療法やサプリメントを試す(医師に相談のうえ)
-
軽いウォーキングやヨガを習慣にする
-
信頼できる人に気持ちを話す
これらはすべて、薬の代わりに「回復の土台」をつくる行為です。
逆に、「薬は飲まないけど何もしない」という状態が続くと、うつが長引いたり、悪化してしまうことがあります。
大切なのは、自分に合うペースと方法で、心と体を整えていくことです。
回復のスピードは人それぞれでいい
うつ病の回復には「時間」が必要です。
薬を使う場合も、使わない場合も、すぐに良くなることはありません。だからこそ、「焦らず」「比べず」「少しずつ」が大切です。
ある男性はこう話していました。
「薬を飲まないと決めて、毎日散歩だけ続けました。最初は苦しかったけど、3か月後には空を見て"きれいだな"と思えるようになりました。」
うつの回復とは、心が少しずつ"感じる力"を取り戻すこと。薬を使う・使わないに関わらず、そのプロセスには価値があります。
まとめ:自分に合った「治し方」を見つけることが一番大切
うつ病の薬に対して不安を感じるのは、決して特別なことではありません。
大切なのは、「薬を飲むか・飲まないか」という二択ではなく、「どうすれば今より少しでも楽に生きられるか」を探すことです。
-
薬を使うことも勇気
-
薬を使わない選択も勇気
-
どちらも「自分を大切にする方法」です
もし迷ったときは、信頼できる医師やカウンセラーに、「自分の気持ちを理解してほしい」と伝えてみてください。専門家は、あなたの「薬を使いたくない気持ち」も含めてサポートしてくれます。
焦らず、少しずつ。回復の道はまっすぐではありませんが、確実に前へ進んでいます。あなたの選択にも、ちゃんと意味があります。
うつ病を治し、再発も予防するためには、生きる目的を見出す必要があります。
多少の失敗でも落ち込むことはなくなります。