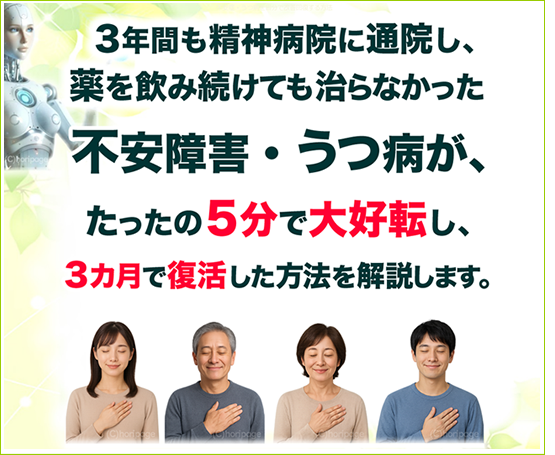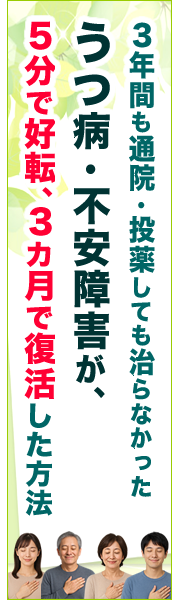うつ病患者さんへの接し方・どう声をかければ良いか
うつ病による自殺防止のための接し方を考えるとき、どう声をかければ良いか・・・もし本人が自殺してしまったら・・・ということも考えてしまいます。
どんな接し方をしても、どんなに最善を尽くしたとしても、愛する人がうつ病自殺で死んだら、支後者は自分を責めてしまいます。
当事者の自殺を防止できる可能性を高めると同時に、不幸にもそれができなかったとしても、周囲の人が「やれるだけの接し方はやった」と思えるような対策を推奨します。人事を尽くして天命を待つ、という方法です。
それは、うつ病患者さんだけでなく支援者も含めて、「マイナスをできるだけ少なくする」という発想です。その、もっとも大切なポイントが、「不調を察知したら(気がついたら)声をかける」という接し方です。
実は声をかけようが声をかけまいが、自殺されたら、後悔するのです。声をかけた場合は、声をかけたのに自分には話してくれなかった、それ以上は対処できなかった、と。
声をかけなかった場合は、なんとなくおかしいと思っていたのに、声をかけなかった...。
もともとどちらもマイナスなのです。だったら、声をかけた接し方のほうがいい。もしかしたら、あなたの声かけによって、当事者が助けを求める可能性があるからです。
実際は「何か変だな」と思っていても、周囲の人も日常生活の中に適当な理由を見つけて、「大したことはないんだ。しばらくすれば立ち直る。様子を見ておこう」と、結局何もしないことが多いのです。
とはいえ、これがなかなか難しい接し方なのです。むやみに声をかけるとかえって、うつ病患者さんの気持ちを逆なでするのではないか、とか自分が声をかけたことで、うつ病患者さんが自分を失い極端な行動に出たらどうしようなどと考えてしまいます。
いきなり心理的なテーマを話題にするのではなく、まず身体的なテーマに関する心配をきっかけに話を進めてほしいのです。
うつ病患者さんとの人間関係に自信がある場合はいきなり、「何か悩んでいることがあるのか」とか「○○のことで困っているのではないか」と切り出してもいいでしょう。
ところが表面飾りが強いうつ病患者さんの場合、どうしても心理面からのアプローチには壁をもうけてしまう傾向があります。
そこで、「最近顔色が良くないような気がするんだけれど、体調はどう」とか「何か疲れているような印象があるのだけど、ちゃんと食事とっている?」などのように体の調子を気遣う言葉から始め、体調管理をテーマにした話題をしばらく続けてみます。
そこから、相手が話し始める状態であれば、本人の苦しみについて耳を傾けます。もしそれ以上話が発展しない場合、「何かあったら相談に乗るからね」という「私はあなたのことを心配しているよ。力になるよ」というメッセージを残して、あっさりと会話を終えてください。
必死になって、それ以上聞き出すことは、かえってうつ病患者さんの心の壁を高くしてしまいます。おそらく、今のタイミングであなたに自分の心の苦しみをを説明することができなかったのです。
あなたに気を使って話しにくかったのか、うつ病の波がたまたま収まっていて、今日は相談しようと思わなかったのか、周りの環境から「ここでは相談できない」と思ったのかはわかりません。
うつ病の方への接し方
―心に寄り添うための声かけと姿勢―
うつ病の方にどう接すればいいのか。身近に苦しんでいる人がいるとき、多くの人が戸惑い、悩みます。
「励ましたいけど、何を言えばいいのか分からない」
「どう声をかけても反応がなくて、余計に距離を感じてしまう」
そんな気持ちを抱くのは自然なことです。
うつ病は、単なる「気持ちの問題」や「怠け」ではありません。脳の働きや神経伝達のバランスが崩れ、エネルギーが極端に落ちた状態です。ですから、本人が「頑張ろう」と思っても、身体も心も動いてくれないのです。
まず、その事実を理解することが、最初の「寄り添い」です。
1. 「励ます」より「認める」ことを大切に
多くの人が最初にしてしまいがちなのが、「励ましの言葉」です。
たとえば、
-
「元気出して」
-
「大丈夫だよ」
-
「もっと外に出てみたら?」
これらは一見、優しい言葉ですが、うつ病の人には"責められているように"聞こえてしまうことがあります。
なぜなら、本人も「元気を出したい」「外に出たい」と思っているのに、それができない自分をすでに責めているからです。
そのため、「頑張って」「元気出して」よりも、次のような言葉が心に届きやすいです。
-
「無理しなくていいよ」
-
「今日はここまでできただけでもすごいね」
-
「つらい中でも話してくれてありがとう」
たとえ小さなことでも、"できたこと"や"感じたこと"を認めてあげることが、心を支える力になります。
2. 「沈黙」も、安心できる空気のひとつ
うつ病の方は、会話すること自体がつらいと感じることがあります。だから、無理に話題を作らなくても構いません。
一緒に静かに過ごす時間も、立派な「支え」になります。
たとえば、
-
隣でお茶を飲むだけ
-
同じ部屋で本を読む
-
テレビをつけておくけれど、お互いに言葉を交わさない
そうした何気ない「沈黙の共有」が、本人にとって「安心していられる場所」になるのです。
沈黙を怖がらず、「ここにいていい」と感じられる雰囲気を作ることが大切です。
3. 「質問攻め」ではなく、「見守る姿勢」
よかれと思って、「どうしたの?」「なぜそんな気持ちになるの?」と理由を聞きたくなることがあります。
ですが、うつ病のときは自分の感情や思考を整理する力が弱まっているため、説明すること自体が負担になることがあります。
代わりに、こんな言葉が効果的です。
-
「話したくなったら、いつでも聞くよ」
-
「今は言葉にならなくても大丈夫」
-
「無理に話さなくてもいいよ」
このような「見守る言葉」は、相手に"安心して沈黙できる権利"を与えます。人は「話してもいい」「話さなくてもいい」と感じたとき、少しずつ心を開けるようになります。
4. 「解決しよう」としない勇気
多くの人は、誰かが苦しんでいると、「どうにかして助けたい」と思います。ですが、うつ病のときに必要なのは、"解決策"ではなく"共感"です。
たとえば、本人が「もう何もかもダメだ」と言ったときに、「そんなことないよ」「頑張れば良くなるよ」と言ってしまうと、本人は「自分のつらさを分かってもらえなかった」と感じてしまうことがあります。
そんなときは、答えを出そうとせず、ただ「その気持ちを受け取る」ことが大切です。
-
「そう感じるほど、つらかったんだね」
-
「本当に頑張ってきたんだね」
-
「今は苦しいよね。そばにいるからね」
"正しい言葉"ではなく、"気持ちを分かろうとする姿勢"が、心に届きます。
5. 「回復の波」を理解して、焦らない
うつ病の回復は、「階段」ではなく「波」のように上下します。少し元気になったと思ったら、また落ち込む。それを見て、「せっかく良くなったのに」「また戻っちゃった」と思うかもしれません。
けれど、それは後退ではなく、「波の中の回復プロセス」です。調子の良い日と悪い日を行き来しながら、少しずつ回復していきます。
そのため、周囲は「良くなった/悪くなった」と一喜一憂せず、長い目で見守ることが大切です。
-
「今日はゆっくり過ごせばいいね」
-
「昨日より少し笑顔が見られて嬉しいよ」
そんなふうに、"今この瞬間"の気持ちを受け止めていくことが、本人の安心につながります。
6. 支える人自身も、無理をしないで
うつ病の方を支えるのは、とてもエネルギーのいることです。「支えなければ」と気を張り続けてしまうと、支える側まで疲れきってしまうことがあります。
だからこそ、支える人自身も「休む」ことが大切です。
-
1人の時間を取る
-
信頼できる人に話す
-
専門家(カウンセラーなど)に相談する
「自分の心を守ること」も、相手を支えるための大事な行動です。支える人が笑顔でいられることが、うつ病の方にとっても安心の源になります。
7. 専門的なサポートを尊重する
うつ病は、医師や心理士などの専門家の治療・支援によって回復が進みます。身近な人ができるのは、その治療を支える"土台"を作ることです。
たとえば、
-
通院や薬の管理をそっと手伝う
-
医師の指示を尊重する
-
「治療を続けてえらいね」と声をかける
といったことが、本人の"治そうという力"を支えます。
逆に、「薬に頼りすぎじゃない?」「病院に行かなくても平気じゃない?」といった言葉は、治療への信頼を揺るがせてしまうことがあります。
専門的な治療と、身近な人の支え。その両方があってこそ、回復への道が開かれます。
8. 「あなたがいてくれてよかった」と伝える
最後に、何よりも大切なのは「存在を肯定する言葉」です。
うつ病の方は、自分を「価値のない人間」と感じてしまうことがあります。
そんなときに必要なのは、「あなたの存在が大切だ」と伝えることです。
-
「あなたがいるだけで安心する」
-
「あなたがここにいることが嬉しい」
-
「いてくれてありがとう」
この言葉は、回復のきっかけになることがあります。うつ病は"孤独との戦い"でもあります。
だからこそ、「あなたは一人じゃない」というメッセージを、言葉でも、態度でも、少しずつ伝えていくことが大切です。
まとめ
うつ病の方への接し方で最も大切なのは、「正しい言葉」ではなく「安心できる関係」です。
無理に励まさなくても、沈黙でも、ただそばにいてくれるだけで、救われることがあります。
そして、支える人自身も「完璧でなくていい」「できる範囲で大丈夫」と思ってください。
うつ病の回復には時間がかかりますが、ゆっくりとした時間の中で、「誰かが自分を理解しようとしてくれた」という記憶が、本人の心を支えていきます。
あなたの優しさは、きっと届いています。
たとえ今は反応がなくても、その温もりは静かに、確かに、心の奥で光っています。
うつ病を治し、再発も予防するためには、生きる目的を見出す必要があります。
多少の失敗でも落ち込むことはなくなります。