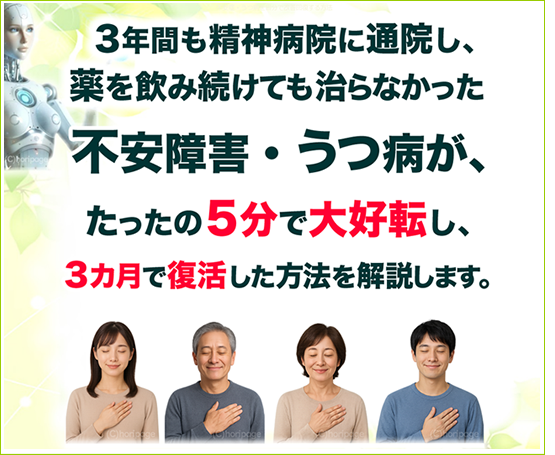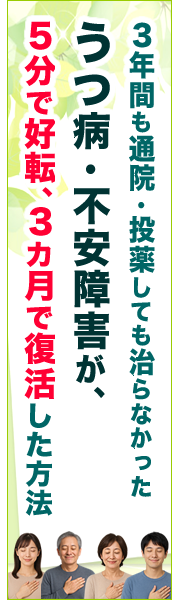うつ病患者さんの話をゆっくり聞く接し方
また、しがみつき行為の中止を直接指示するものではなくても、現状を打開するために「何かをしてみたら」という接し方も当初のうちは控えなければいけません。
たとえば人間関係で悩んでいると訴える、うつ病患者さんに対して、「正しいことを辛抱強く続けていれば、きっといつか相手だってわかってくれるよ」とか「こちらから積極的に挨拶をしていくことから始めたら」などと言うのは、エネルギーの枯渇しているうつ病患者さんに、新たなエネルギーの支出を要求することになります。
うつ病患者さんは、今の生き方を維持するだけで精一杯なのです。たとえ悪くなる方向への生活態度や行動でも、急にハンドルを切ることを強要されることが一番苦しいのです。ハンドルは本人が切れる範囲で、徐々に切っていく。急ハンドル禁止なのです。
また、枯渇するエネルギーにおびえるうつ病患者さんは、長い時間がんばるという発想ができません。それはまるで沈みゆく船で全員がバケツで水をかき出す作業を命じられるようなものです。とても今はそんな状況ではないのです。
つまり新しいこと、長くかかることは受け入れがたいのです。そのようなアドバイスはやはり現場をわかっていない人からの接し方として受け取られます。
ところが「新たに何かすることをやめる」を拡大解釈し、当事者に何もしないことを要求すると、逆に苦しくなってしまいます。その意味では、結果的にうつ病患者さんの正しい対応である「受診する。休みを取る」というアドバイスでさえも、当初は控えなければいけません。
走っているのに、「止まれ」はだめなのです。急ブレーキも禁止。今の走りでいいよ、そのままで大丈夫だよと言ってやる。これが一番エネルギーを使わないのです。その走りで落ち着いてから方向転換を指示しましょう。
うつ病患者さんの話をゆっくり聞く接し方
〜心を守る「傾聴」の力〜
うつ病の方と向き合うとき、最も大切なのは「話を聞く姿勢」です。
どんなに励まそうとしても、相手が「分かってもらえなかった」と感じてしまえば、心の距離はかえって広がってしまいます。
ここでは、うつ病の方に安心感を与え、少しずつ心を開いてもらうための「ゆっくり聞く接し方」を、やさしく具体的に解説します。
1. 話を「聞く」ことは、「支える」こと
うつ病の方は、自分の気持ちを言葉にするだけでも大きなエネルギーを使います。
そのため、話の内容よりも、「聞いてくれる人がいる」という事実が支えになるのです。
たとえば、こんな会話があります。
患者さん:「もう何もやる気が出ないんです...。」
聞き手:「そうなんですね。最近、特にしんどい日が多いですか?」
このように、相手の言葉を否定せず、そのまま受け止めるだけで安心感が生まれます。
アドバイスをしなくても、「この人は自分の話をちゃんと聞いてくれている」と感じることが、心の回復の第一歩になります。
2. 急かさない。「沈黙」も大切な時間
うつ病の方の話には、沈黙が多くなることがあります。
何を話していいか分からなかったり、言葉を選ぶのに時間がかかったりするためです。
このとき大事なのは、「沈黙を怖がらないこと」です。
多くの人は、沈黙が続くと気まずくなって、つい話題を変えたり、励ましの言葉を入れたりしてしまいます。
でも、それがかえって相手に「急かされている」「分かってもらえない」と感じさせてしまうこともあります。
たとえばこんな場面。
患者さん:「...最近、眠れないんです。」
聞き手:「そうなんですね。眠れないとつらいですよね。」
(少し沈黙)
聞き手:「もしよかったら、どんなときに眠れなくなるのか、教えてもらえますか?」
沈黙のあとに、やさしく問いかけることで、相手のペースを尊重しながら話を続けることができます。
「ゆっくりで大丈夫ですよ」という雰囲気をつくることが、信頼関係を深めるカギになります。
3. 「励まし」よりも「共感」を
うつ病の方に対して、「頑張って」「前向きに考えよう」という言葉は、励ましのつもりでもプレッシャーになることがあります。
うつ病は、意志や根性の問題ではなく、脳と心のバランスが崩れている状態だからです。
たとえばこう言われたら、どう感じるでしょうか?
「そんなに落ち込まないで、もっと楽しいこと考えようよ!」
元気なときなら励ましに聞こえますが、うつ状態のときは「自分はダメなんだ」と感じさせてしまうことがあります。
代わりに、こんな言葉を使ってみてください。
「つらいですよね。よく話してくれましたね。」
「無理に元気にならなくていいですよ。」
「今の気持ちを教えてくれて、ありがとう。」
「分かってもらえた」と感じられる言葉は、どんな薬よりも心を落ち着かせてくれます。
共感は、相手の心に「安心」という灯をともします。
4. 話を「整理」しようとしない
話を聞いていると、「こうすればいいのに」とアドバイスしたくなる瞬間があります。
しかし、うつ病の方は、頭では分かっていても行動に移せない状態です。
そのため、正論や解決策を示されると、「できない自分」を責めてしまうことがあります。
たとえば、
「そんなに悩むことないよ」
「外に出たら気分変わるよ」
という言葉は、一見ポジティブですが、相手を否定するメッセージにもなります。
代わりに、こんな受け止め方をしてみましょう。
「それだけつらいんですね。」
「外に出るのも難しいくらい、今はしんどいんですね。」
話の「内容」よりも、「感情」に寄り添うことが大切です。
相手が安心して気持ちを吐き出せる場をつくることが、回復を支える何よりの力になります。
5. 表情や声のトーンにも「寄り添い」を
うつ病の方は、言葉だけでなく、表情や声のトーンにも敏感です。
早口で話したり、明るすぎる声で励ましたりすると、無意識に距離を感じさせてしまうことがあります。
話すときは、少しゆっくりと、やさしい声で。まるで「安心の毛布」で包み込むようなイメージで接してみましょう。
また、相手の表情や姿勢を観察することも大切です。
目を合わせたくなさそうなら、無理に正面から向き合わなくてもかまいません。
同じ方向を見ながら話す「並んで聞く姿勢」も、安心感を与える方法のひとつです。
6. 聞き手も「無理をしない」
うつ病の方を支える立場の人は、知らず知らずのうちに自分まで疲れてしまうことがあります。
「何とかしてあげたい」と思う優しさが、重荷になってしまうことも少なくありません。
大切なのは、「自分ができる範囲」で寄り添うことです。
すべてを背負おうとせず、専門家(医師・心理士など)の助けを借りるのも立派なサポートの一部です。
「あなたがいてくれるだけで救われた」
そう思ってもらえるだけでも、十分に価値のあることです。
焦らず、長い目で見守りましょう。
7. 「聞くこと」は「愛情のかたち」
ゆっくり話を聞くというのは、決して受け身なことではありません。
相手の世界にそっと寄り添い、安心できる場所を一緒に作っていく「積極的な優しさ」です。
たとえば、こんなシーンを思い浮かべてください。
うつ病の友人が、涙をこらえながら「もう生きてる意味が分からない」と言ったとき。
その場で何も言えなくても、ただそばで静かにうなずいてくれる人がいたら、
その沈黙は、「あなたの存在を否定しない」という強いメッセージになります。
うつ病の方にとって、話を聞いてもらうことは「生きる力」を取り戻すきっかけになります。
聞き手がそのことを理解し、やさしい気持ちで接してくれるだけで、心の中に小さな希望が芽生えるのです。
まとめ:ゆっくり、やさしく、受け止める
うつ病患者さんの話を聞くときに大切なのは、次の3つです。
-
否定せず、ありのままを受け止める
-
沈黙を恐れず、相手のペースに合わせる
-
共感の言葉で「安心できる空気」をつくる
相手を変えようとするのではなく、「一緒にそこにいる」ことが支えになります。
そして、どんな小さな会話でも、うつ病の方にとっては大切な「回復のきっかけ」になるのです。
ゆっくり聞くことは、時間がかかるように思えて、実は最も確かな近道です。
焦らず、やさしく、心を寄せていきましょう。
うつ病を治し、再発も予防するためには、生きる目的を見出す必要があります。
多少の失敗でも落ち込むことはなくなります。