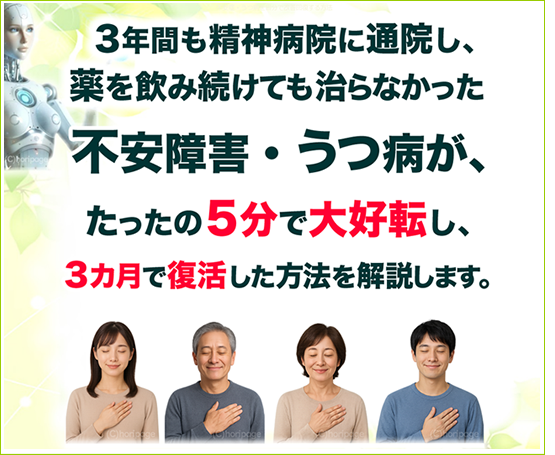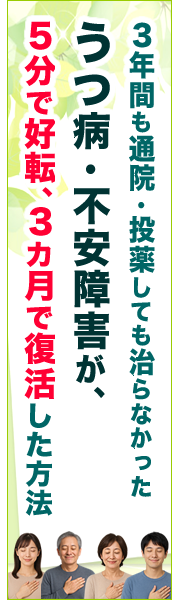うつ病の病院での治療法とは
もちろん、生活や仕事を調整して休養を取ることを勧められるでしょう。もし、自宅で休養が取れない場合や、死にたい気持ちが強いのに家族の誰も対処できない場合などは、入院治療を勧められます。
病院の精神科では、基本的に本人が了解しない限り、強制的に入院させられることはありません。うつ病の場合は入院しても、特別な治療が待っているわけではありません。
うつ病の原因は、疲労蓄積しているのが普通ですから、薬で眠れるようになると、ずっと寝ているのが一般的です。1・2週間そんな生活をしていると、だんだん治療回復してきて歩けるようになります。
本を読んだり、TVを見たり、自分のペースで少しずつ活動できるようになります。そうすると、カウンセリングを受けたり、簡単な体操や散歩を始めるのです。
うつ病の治療は、他の病気をした人がリハビリする過程とほとんど変わらないのです。病院の精神科に入院するとなると、何か恐ろしい治療を受けるものと勘違いされていますが、そんなことはありません。
ほとんどの病院では、この薬物療法と環境調整、入院でうつ病治療に対処してくれますが、病院や担当の医師や心理療法士によっては、カウンセリングの中でも認知療法という方法や、体を刺激するTFT(思考場療法)、電気けいれん療法などを使うこともあります。
電気けいれん療法は、電気ショックを使うため怖いというイメージを持ちがちですが、長引く方や、薬があまり効かない方でも効果が見られることもありますので、医師が勧める場合には、よく説明を聞いてみてください。
TFTも即効感があり、この療法が合う人には効果的でしょう。しかし、うつ病状態の根本は疲労であることを忘れないでください。一発ですべてが解決(リセット)し、完全に以前の元気な自分に戻れるという療法はないのです。
ただこのような治療法で、うつ病の悪循環が好循環に変わるきっかけが得られるかもしれません。医師と相談して、自分と合うかどうかよく検討して、恐れず試してみてください。
うつ病の病院での治療法とは?やさしくわかる基本と回復へのステップ
「気持ちが沈んで、何をしても楽しく感じられない」「朝起きるのがつらい」「仕事や家事に手がつかない」
こうした状態が続くと、「もしかしてうつ病かもしれない」と不安になる方も多いでしょう。
うつ病は心の病というよりも、脳の働きのバランスが崩れて起こる"体の病気"です。決して「気の持ちよう」や「根性の問題」ではありません。
そして、適切な治療を受けることで、多くの人が回復しています。
この記事では、病院で行われるうつ病の治療法について、やさしく解説していきます。
1. まずは「受診すること」から始まります
うつ病の治療は、心療内科や精神科での受診からスタートします。
「そんな大げさなところに行くのは抵抗がある...」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、心療内科は「心と体の調子がつながっている」と考える医療機関で、決して特別な場所ではありません。
たとえば、次のような症状が2週間以上続く場合は、一度相談してみることをおすすめします。
(参照→うつ病の診断セルフチェック判定テスト&症状の解説)-
眠れない、または眠りすぎてしまう
-
食欲がない、または過食してしまう
-
朝が特につらい
-
何をしても楽しく感じられない
-
自分を責めてしまう
-
集中力が落ちて、ミスが増えた
これらはうつ病の典型的なサインです。
早めに受診することで、治療がスムーズに進み、回復までの時間も短くなります。
2. 診断の流れ ― 医師はどのようにうつ病を見極めるのか
病院では、医師が問診(インタビュー)を中心に診断を行います。
「いつから調子が悪いか」「どんな場面でつらいと感じるか」「睡眠や食欲の状態」「仕事や家庭の状況」などを丁寧に聞き取ります。
必要に応じて、血液検査や脳の検査を行うこともあります。
これは、甲状腺の異常や貧血など、うつ病に似た症状を引き起こす他の病気を除外するためです。
診断が確定した後は、症状の重さや生活環境に合わせて、治療方針が立てられます。
3. 病院で行われる主な治療法
うつ病の治療にはいくつかの柱があります。
どれか一つだけで治すというよりも、薬・休養・カウンセリングなどを組み合わせていくのが一般的です。
(1) 薬物療法 ― 脳内バランスを整えるサポート
うつ病の治療でもっとも一般的なのが抗うつ薬による薬物療法です。
うつ病では、脳内の「セロトニン」「ノルアドレナリン」「ドーパミン」といった神経伝達物質の働きが低下しています。
抗うつ薬は、このバランスを整え、気分を安定させる役割を持ちます。
代表的な薬には、次のようなタイプがあります。
-
SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
→ 比較的副作用が少なく、初期治療でよく使われます。 -
SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)
→ 気分の落ち込みだけでなく、倦怠感や集中力の低下にも効果が期待されます。 -
NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)
→ 睡眠の質を改善する作用もあるため、眠れないタイプのうつに用いられます。
薬の効果はすぐに現れるものではなく、2~4週間ほどかけてゆっくり効いてくるのが特徴です。焦らず、医師の指示どおりに飲み続けることが大切です。
(2) 精神療法(カウンセリング) ― 心の整理を手伝う治療
薬だけでなく、カウンセリング(心理療法)も重要な治療の柱です。
心のつらさを言葉にし、感情を整理していくことで、少しずつ前向きな視点を取り戻していけます。
代表的な方法としては、
-
認知行動療法(CBT)
→ 「自分を責めすぎてしまう」「失敗を過大に受け止めてしまう」といった思考のクセを見直し、より現実的で優しい考え方を育てていく方法です。(参照→認知行動療法(CBT)の目的・効果・やり方の解説) -
対人関係療法(IPT)
→ 人間関係のストレスや孤立感に焦点を当て、対話や関係性の改善を目指します。 -
支持的精神療法
→ 医師やカウンセラーが話を丁寧に聴き、「あなたの気持ちは自然なことですよ」と受け止めながらサポートする、穏やかなアプローチです。
自分に合う方法を見つけるまでに少し時間がかかることもありますが、「話を聴いてもらうだけで少し楽になった」という方はとても多いです。
(3) 休養 ― 心と体をリセットする時間
うつ病の回復には、十分な休養も欠かせません。
無理をして仕事や家事を続けると、脳の疲れが回復しないまま、症状が長引いてしまうことがあります。
医師が「しばらく休みましょう」と言うのは、「怠けなさい」という意味ではありません。
むしろ、脳のエネルギーを回復させるための"治療"です。
休養中は、次のような過ごし方が良いとされています。
-
朝は同じ時間に起きて、生活リズムを整える
-
無理に何かをしようとせず、体が求めるだけ休む
-
散歩やストレッチなど、気分転換になる軽い運動をする
-
スマホやSNSを見すぎないようにする
しばらく休むことで、頭の中の霧が少しずつ晴れていく感覚が戻ってきます。
4. 回復までの道のり ― あせらず「波」を受け入れる
うつ病の回復は、まっすぐ右肩上がりではなく、良くなったり悪くなったりを繰り返す波のような経過をたどります。
「昨日より少し元気が出た」「今日はまた沈んでしまった」というのは自然なことです。
たとえば、登山でいうなら、休憩を取りながら少しずつ頂上に近づいていくようなもの。
焦ってスピードを上げると途中で息切れしてしまうので、"ゆっくり"が一番の近道なのです。
5. 家族や周囲の理解も大切に
うつ病は本人だけでなく、家族や職場の理解も大切です。
「頑張って」「元気出して」といった言葉は、良かれと思って言っても、本人にはプレッシャーになることがあります。
代わりに、こんな言葉をかけてみましょう。
-
「無理しなくていいよ」
-
「あなたのペースで大丈夫」
-
「話したくなったら、いつでも聞くよ」
その一言が、本人にとって大きな支えになります。
6. まとめ ― 治療は「再び笑顔を取り戻すためのプロセス」
うつ病の治療は、
-
医師の診断
-
薬物療法
-
カウンセリング
-
休養
そして、うつ病は正しく治療すれば回復できる病気です。
やがて、心が少しずつ軽くなり、「また笑える日」が戻ってきます。
うつ病を治し、再発も予防するためには、生きる目的を見出す必要があります。
多少の失敗でも落ち込むことはなくなります。