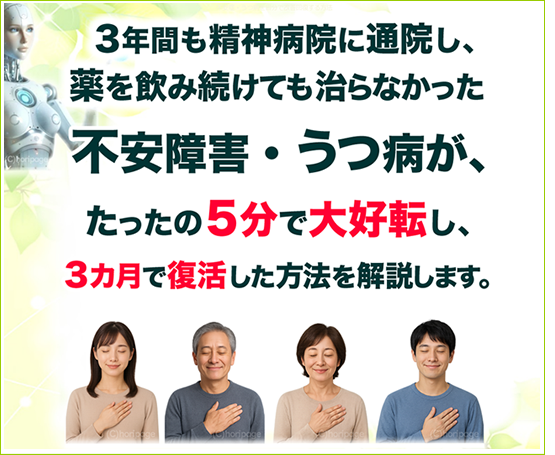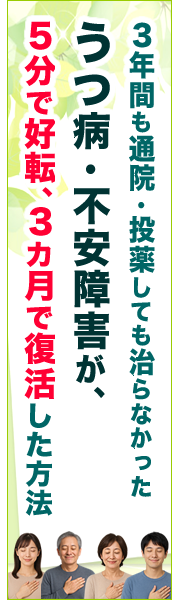うつ病患者への正しい接し方・原則とは
うつ病状態の「死にたい気持ち」を抱える当事者を支援する上では、「当事者の生き方、対処の方法を変えない」という接し方を覚えてほしいのです。
これは非常に難しい接し方ですが、意識することによって何とか支援者自身の行動をコントロールできると思います。この接し方の原則に従わないと、別人になったうつ病患者の心を開くことがなかなか難しくなります。
この接し方は、たとえばこういうことです。
・手首を切る癖のあるうつ病患者に対して、「手首を切るな」と言わない。
・アルコールを飲んで死にたい気持ちが生じるうつ病患者に対して「アルコールを飲むな」と言わない。
・自殺未遂をしたうつ病患者に対して「二度とそんなことはするな」と言わない。
・虐待をしてしまううつ病患者に対して「虐待をするな」と言わない。
・ギャンブルに手を出し消費者金融から借りてしまううつ病患者に対し「ギャンブルをするな」と言わない。
・休みたくないといううつ病患者に対し「休め」と言わない。
・そして「死にたい」と言ううつ病患者に対して「そんなこと言うな」と言わない。
それらは難しく、何となくおかしいことはわかっています。ところがこれが「うつ病患者への接し方の原則」なのです。
まずわかっていただきたいのは、最後までこの原則通りにするわけではないということです。周囲の人が支援をする当初、当事者と心を結ぶまでの間、この接し方の原則に従っていただきたいのです。
支援の途中でも、うつ病患者の調子が崩れ支援者との交流が難しくなった場合は、この原則に戻っていただきたいと思います。
周囲がうつ病患者の不調に気づくのは、しがみつき行為が表面に現れている場合が多いのです。するとどうしてもそのしがみつき行為に対して、意識が向いてしまいます。
しかし、しがみつき行為はうつ病患者が生きるために必死の思いでやっている行動です。それを最初に否定されると、当事者は簡単に殼に閉じこもってしまいます。
うつ病患者への正しい接し方・原則(やさしく寄り添うための実践ガイド)
うつ病の方と接するときは、「治す」より「寄り添う」ことが先です。治療は医師や専門家の仕事ですが、日常でそばにいる人の言葉や態度が回復を支える大きな力になります。
うつ病の方と接するときは、「治す」より「寄り添う」ことが先です。治療は医師や専門家の仕事ですが、日常でそばにいる人の言葉や態度が回復を支える大きな力になります。
以下は、具体例を交えた原則と実践的な言い回し・注意点です。家族、友人、同僚、支援者向けに分かりやすくまとめます。
1. 相手の感情をまず受け止める(否定しない)
原則:感情を否定したり、すぐ解決しようとしたりしない。
1. 相手の感情をまず受け止める(否定しない)
原則:感情を否定したり、すぐ解決しようとしたりしない。
実践例:「そんなことで落ち込むなんて」「前は元気だったのに」と言わない。代わりに「今は本当にしんどいんだね」「話してくれてありがとう」と受け止める。短くても「つらかったね」と共感する一言が安心感になります。
2. 聞く姿勢を優先する(話す場所と時間を作る)
原則:傾聴は治療の補助になる。判断や指示は後回し。
2. 聞く姿勢を優先する(話す場所と時間を作る)
原則:傾聴は治療の補助になる。判断や指示は後回し。
実践例:スマホを置き、目線を合わせ、相手が話すペースに合わせる。「今、話してもいい?」と確認してから聞く。沈黙が続いても焦らず、無理に話させない。
3. 指示・説教・励ましの乱発は避ける
原則:意図は良くても「頑張れ」「気の持ちようだよ」といった言葉は逆効果になりがち。
3. 指示・説教・励ましの乱発は避ける
原則:意図は良くても「頑張れ」「気の持ちようだよ」といった言葉は逆効果になりがち。
実践例:代わりに具体的で小さい提案をする。「今日は服を着替えるだけでいいよ。一緒にシャツを選ぼうか?」のように、達成しやすい目標を一緒に立てる。
4. 事実確認と助言は専門家と連携して行う
原則:治療方針や薬の変更など医療的事項は専門家に委ねる。
4. 事実確認と助言は専門家と連携して行う
原則:治療方針や薬の変更など医療的事項は専門家に委ねる。
実践例:「医師に相談してみるのはどうかな。もし一緒に行ってほしいなら付き添うよ」と提案する。本人が受診を拒む場合は無理強いせず、受診のメリットを優しく伝える。
5. 日常の支援は具体的に(家事・連絡・手続き)
原則:抽象的な「何でも言ってね」より、具体的な支援の申し出が効果的。
5. 日常の支援は具体的に(家事・連絡・手続き)
原則:抽象的な「何でも言ってね」より、具体的な支援の申し出が効果的。
実践例:「今週の買い物、私がやっておくよ」「明日の朝、ご飯だけ作っておくね」「病院の予約、代わりに調べてもいい?」など、ほんの少しの手助けが相手の負担を軽くします。
6. 境界線を守る(自分の心の健康も大切)
原則:支える側が疲弊すると長続きしない。助け方の範囲を決める。
6. 境界線を守る(自分の心の健康も大切)
原則:支える側が疲弊すると長続きしない。助け方の範囲を決める。
実践例:「夜中はすぐ対応できないけど、朝になったら必ず連絡するね」とルールを作る。必要なら他の家族や専門機関と役割分担をする。
7. 表情・態度で安心を伝える
原則:言葉だけでなく非言語コミュニケーションが重要。
7. 表情・態度で安心を伝える
原則:言葉だけでなく非言語コミュニケーションが重要。
実践例:やわらかい声のトーンで、強いジャッジは避ける。短いハグや手を握るなど、相手が触れ合いを嫌がらなければ物理的な安心も有効です。
8. 小さな変化を見逃さない(悪化のサインへの対応)
原則:自殺念慮、極端な無関心、食事や睡眠の異常などはリスクサイン。
8. 小さな変化を見逃さない(悪化のサインへの対応)
原則:自殺念慮、極端な無関心、食事や睡眠の異常などはリスクサイン。
実践例:普段より悲観的な言葉が増えたり、日常生活がほとんどできなくなったら早めに専門家へ相談する。本人が危険を示唆する発言をした場合は軽く扱わず、緊急の対応(医療機関や相談窓口)を検討する。
9. 言って良いこと、悪いこと(具体的フレーズ)
言って良いこと:
「今の気持ちを教えてくれてありがとう」
「一緒にいるよ。無理しなくていいよ」
「今日は何をしたい?小さなことでいいよ」
避けるべき言葉:
「甘えだよ」「そんなことで悩むな」
「気合で直せばいい」「前はできたのに」
比較や責める表現(例:「あの人はもっと頑張っている」)
10. 継続的な支援と希望の伝え方
原則:回復には時間がかかる。すぐに元気にならなくても続けて支える姿勢を伝える。
9. 言って良いこと、悪いこと(具体的フレーズ)
言って良いこと:
「今の気持ちを教えてくれてありがとう」
「一緒にいるよ。無理しなくていいよ」
「今日は何をしたい?小さなことでいいよ」
避けるべき言葉:
「甘えだよ」「そんなことで悩むな」
「気合で直せばいい」「前はできたのに」
比較や責める表現(例:「あの人はもっと頑張っている」)
10. 継続的な支援と希望の伝え方
原則:回復には時間がかかる。すぐに元気にならなくても続けて支える姿勢を伝える。
実践例:「今はつらいけど、あなたが一人じゃないことを忘れないで」「小さな一歩でも一緒に喜ぼう」と伝え、具体的に次にできそうなことを一緒に考える。
最後に(まとめ)
うつ病の方への正しい接し方は、受け止める・寄り添う・具体的に助ける・自分を守るのバランスです。
最後に(まとめ)
うつ病の方への正しい接し方は、受け止める・寄り添う・具体的に助ける・自分を守るのバランスです。
一言で言えば「判断しないで、共にいる」こと。
もし自分ひとりで抱えきれないと感じたら、信頼できる家族や医療機関、相談窓口に助けを求めることも大切です。
あなたのささやかな配慮と継続的な支えが、相手にとって何よりの支えになります。
うつ病を治し、再発も予防するためには、生きる目的を見出す必要があります。
生きる意味、生きる目的がしっかりできれば、
毎日充実した気分で過ごせますし、
多少の失敗でも落ち込むことはなくなります。
多少の失敗でも落ち込むことはなくなります。
生きる目的を見出し、脳機能と潜在意識を整えて、うつ病を治す方法は、以下のサイトが参考になります。
参考サイト→ うつ病の治し方【不安うつクリア】