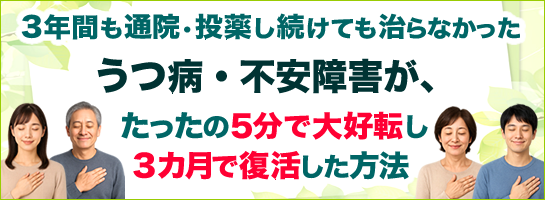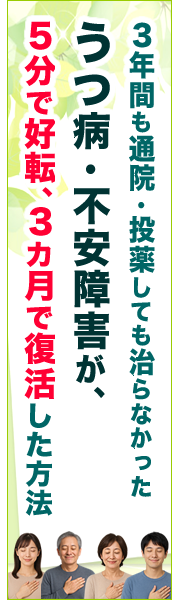うつ病の人との接し方
うつ病状態の「死にたい気持ち」を抱える当事者を支援する上では、「当事者の生き方、対処の方法を変えない」という接し方を覚えてほしいのです。
これは非常に難しい接し方ですが、意識することによって何とか支援者自身の行動をコントロールできると思います。この接し方の原則に従わないと、別人になったうつ病患者の心を開くことがなかなか難しくなります。
この接し方は、たとえばこういうことです。
・手首を切る癖のあるうつ病患者に対して、「手首を切るな」と言わない。
・アルコールを飲んで死にたい気持ちが生じるうつ病患者に対して「アルコールを飲むな」と言わない。
・自殺未遂をしたうつ病患者に対して「二度とそんなことはするな」と言わない。
・虐待をしてしまううつ病患者に対して「虐待をするな」と言わない。
・ギャンブルに手を出し消費者金融から借りてしまううつ病患者に対し「ギャンブルをするな」と言わない。
・休みたくないといううつ病患者に対し「休め」と言わない。
・そして「死にたい」と言ううつ病患者に対して「そんなこと言うな」と言わない。
それらは難しく、何となくおかしいことはわかっています。ところがこれが「うつ病患者への接し方の原則」なのです。
まずわかっていただきたいのは、最後までこの原則通りにするわけではないということです。周囲の人が支援をする当初、当事者と心を結ぶまでの間、この接し方の原則に従っていただきたいのです。
支援の途中でも、うつ病患者の調子が崩れ支援者との交流が難しくなった場合は、この原則に戻っていただきたいと思います。
周囲がうつ病患者の不調に気づくのは、しがみつき行為が表面に現れている場合が多いのです。するとどうしてもそのしがみつき行為に対して、意識が向いてしまいます。
うつ病の方と接するときは、「治す」より「寄り添う」ことが先です。治療は医師や専門家の仕事ですが、日常でそばにいる人の言葉や態度が回復を支える大きな力になります。
1. 相手の感情をまず受け止める(否定しない)
原則:感情を否定したり、すぐ解決しようとしたりしない。
2. 聞く姿勢を優先する(話す場所と時間を作る)
原則:傾聴は治療の補助になる。判断や指示は後回し。
3. 指示・説教・励ましの乱発は避ける
原則:意図は良くても「頑張れ」「気の持ちようだよ」といった言葉は逆効果になりがち。
4. 事実確認と助言は専門家と連携して行う
原則:治療方針や薬の変更など医療的事項は専門家に委ねる。
5. 日常の支援は具体的に(家事・連絡・手続き)
原則:抽象的な「何でも言ってね」より、具体的な支援の申し出が効果的。
6. 境界線を守る(自分の心の健康も大切)
原則:支える側が疲弊すると長続きしない。助け方の範囲を決める。
7. 表情・態度で安心を伝える
原則:言葉だけでなく非言語コミュニケーションが重要。
8. 小さな変化を見逃さない(悪化のサインへの対応)
原則:自殺念慮、極端な無関心、食事や睡眠の異常などはリスクサイン。
9. 言って良いこと、悪いこと(具体的フレーズ)
言って良いこと:
「今の気持ちを教えてくれてありがとう」
「一緒にいるよ。無理しなくていいよ」
「今日は何をしたい?小さなことでいいよ」
避けるべき言葉:
「甘えだよ」「そんなことで悩むな」
「気合で直せばいい」「前はできたのに」
比較や責める表現(例:「あの人はもっと頑張っている」)
10. 継続的な支援と希望の伝え方
原則:回復には時間がかかる。すぐに元気にならなくても続けて支える姿勢を伝える。
最後に(まとめ)
うつ病の方への正しい接し方は、受け止める・寄り添う・具体的に助ける・自分を守るのバランスです。
うつ病を治し、再発も予防するためには、生きる目的を見出す必要があります。
多少の失敗でも落ち込むことはなくなります。
また、しがみつき行為の中止を直接指示するものではなくても、現状を打開するために「何かをしてみたら」という接し方も当初のうちは控えなければいけません。
たとえば人間関係で悩んでいると訴える、うつ病患者さんに対して、「正しいことを辛抱強く続けていれば、きっといつか相手だってわかってくれるよ」とか「こちらから積極的に挨拶をしていくことから始めたら」などと言うのは、エネルギーの枯渇しているうつ病患者さんに、新たなエネルギーの支出を要求することになります。
うつ病患者さんは、今の生き方を維持するだけで精一杯なのです。たとえ悪くなる方向への生活態度や行動でも、急にハンドルを切ることを強要されることが一番苦しいのです。ハンドルは本人が切れる範囲で、徐々に切っていく。急ハンドル禁止なのです。
また、枯渇するエネルギーにおびえるうつ病患者さんは、長い時間がんばるという発想ができません。それはまるで沈みゆく船で全員がバケツで水をかき出す作業を命じられるようなものです。とても今はそんな状況ではないのです。
つまり新しいこと、長くかかることは受け入れがたいのです。そのようなアドバイスはやはり現場をわかっていない人からの接し方として受け取られます。
ところが「新たに何かすることをやめる」を拡大解釈し、当事者に何もしないことを要求すると、逆に苦しくなってしまいます。その意味では、結果的にうつ病患者さんの正しい対応である「受診する。休みを取る」というアドバイスでさえも、当初は控えなければいけません。
走っているのに、「止まれ」はだめなのです。急ブレーキも禁止。今の走りでいいよ、そのままで大丈夫だよと言ってやる。これが一番エネルギーを使わないのです。その走りで落ち着いてから方向転換を指示しましょう。
うつ病患者さんの話をゆっくり聞く接し方
〜心を守る「傾聴」の力〜
うつ病の方と向き合うとき、最も大切なのは「話を聞く姿勢」です。
どんなに励まそうとしても、相手が「分かってもらえなかった」と感じてしまえば、心の距離はかえって広がってしまいます。
ここでは、うつ病の方に安心感を与え、少しずつ心を開いてもらうための「ゆっくり聞く接し方」を、やさしく具体的に解説します。
1. 話を「聞く」ことは、「支える」こと
うつ病の方は、自分の気持ちを言葉にするだけでも大きなエネルギーを使います。
そのため、話の内容よりも、「聞いてくれる人がいる」という事実が支えになるのです。
たとえば、こんな会話があります。
患者さん:「もう何もやる気が出ないんです...。」
聞き手:「そうなんですね。最近、特にしんどい日が多いですか?」
このように、相手の言葉を否定せず、そのまま受け止めるだけで安心感が生まれます。
アドバイスをしなくても、「この人は自分の話をちゃんと聞いてくれている」と感じることが、心の回復の第一歩になります。
2. 急かさない。「沈黙」も大切な時間
うつ病の方の話には、沈黙が多くなることがあります。
何を話していいか分からなかったり、言葉を選ぶのに時間がかかったりするためです。
このとき大事なのは、「沈黙を怖がらないこと」です。
多くの人は、沈黙が続くと気まずくなって、つい話題を変えたり、励ましの言葉を入れたりしてしまいます。
でも、それがかえって相手に「急かされている」「分かってもらえない」と感じさせてしまうこともあります。
たとえばこんな場面。
患者さん:「...最近、眠れないんです。」
聞き手:「そうなんですね。眠れないとつらいですよね。」
(少し沈黙)
聞き手:「もしよかったら、どんなときに眠れなくなるのか、教えてもらえますか?」
沈黙のあとに、やさしく問いかけることで、相手のペースを尊重しながら話を続けることができます。
「ゆっくりで大丈夫ですよ」という雰囲気をつくることが、信頼関係を深めるカギになります。
3. 「励まし」よりも「共感」を
うつ病の方に対して、「頑張って」「前向きに考えよう」という言葉は、励ましのつもりでもプレッシャーになることがあります。
うつ病は、意志や根性の問題ではなく、脳と心のバランスが崩れている状態だからです。
たとえばこう言われたら、どう感じるでしょうか?
「そんなに落ち込まないで、もっと楽しいこと考えようよ!」
元気なときなら励ましに聞こえますが、うつ状態のときは「自分はダメなんだ」と感じさせてしまうことがあります。
代わりに、こんな言葉を使ってみてください。
「つらいですよね。よく話してくれましたね。」
「無理に元気にならなくていいですよ。」
「今の気持ちを教えてくれて、ありがとう。」
「分かってもらえた」と感じられる言葉は、どんな薬よりも心を落ち着かせてくれます。
共感は、相手の心に「安心」という灯をともします。
4. 話を「整理」しようとしない
話を聞いていると、「こうすればいいのに」とアドバイスしたくなる瞬間があります。
しかし、うつ病の方は、頭では分かっていても行動に移せない状態です。
そのため、正論や解決策を示されると、「できない自分」を責めてしまうことがあります。
たとえば、
「そんなに悩むことないよ」
「外に出たら気分変わるよ」
という言葉は、一見ポジティブですが、相手を否定するメッセージにもなります。
代わりに、こんな受け止め方をしてみましょう。
「それだけつらいんですね。」
「外に出るのも難しいくらい、今はしんどいんですね。」
話の「内容」よりも、「感情」に寄り添うことが大切です。
相手が安心して気持ちを吐き出せる場をつくることが、回復を支える何よりの力になります。
5. 表情や声のトーンにも「寄り添い」を
うつ病の方は、言葉だけでなく、表情や声のトーンにも敏感です。
早口で話したり、明るすぎる声で励ましたりすると、無意識に距離を感じさせてしまうことがあります。
話すときは、少しゆっくりと、やさしい声で。まるで「安心の毛布」で包み込むようなイメージで接してみましょう。
また、相手の表情や姿勢を観察することも大切です。
目を合わせたくなさそうなら、無理に正面から向き合わなくてもかまいません。
同じ方向を見ながら話す「並んで聞く姿勢」も、安心感を与える方法のひとつです。
6. 聞き手も「無理をしない」
うつ病の方を支える立場の人は、知らず知らずのうちに自分まで疲れてしまうことがあります。
「何とかしてあげたい」と思う優しさが、重荷になってしまうことも少なくありません。
大切なのは、「自分ができる範囲」で寄り添うことです。
すべてを背負おうとせず、専門家(医師・心理士など)の助けを借りるのも立派なサポートの一部です。
「あなたがいてくれるだけで救われた」
そう思ってもらえるだけでも、十分に価値のあることです。
焦らず、長い目で見守りましょう。
7. 「聞くこと」は「愛情のかたち」
ゆっくり話を聞くというのは、決して受け身なことではありません。
相手の世界にそっと寄り添い、安心できる場所を一緒に作っていく「積極的な優しさ」です。
たとえば、こんなシーンを思い浮かべてください。
うつ病の友人が、涙をこらえながら「もう生きてる意味が分からない」と言ったとき。
その場で何も言えなくても、ただそばで静かにうなずいてくれる人がいたら、
その沈黙は、「あなたの存在を否定しない」という強いメッセージになります。
うつ病の方にとって、話を聞いてもらうことは「生きる力」を取り戻すきっかけになります。
聞き手がそのことを理解し、やさしい気持ちで接してくれるだけで、心の中に小さな希望が芽生えるのです。
まとめ:ゆっくり、やさしく、受け止める
うつ病患者さんの話を聞くときに大切なのは、次の3つです。
-
否定せず、ありのままを受け止める
-
沈黙を恐れず、相手のペースに合わせる
-
共感の言葉で「安心できる空気」をつくる
相手を変えようとするのではなく、「一緒にそこにいる」ことが支えになります。
そして、どんな小さな会話でも、うつ病の方にとっては大切な「回復のきっかけ」になるのです。
ゆっくり聞くことは、時間がかかるように思えて、実は最も確かな近道です。
焦らず、やさしく、心を寄せていきましょう。
うつ病を治し、再発も予防するためには、生きる目的を見出す必要があります。
多少の失敗でも落ち込むことはなくなります。
うつ病による自殺防止のための接し方を考えるとき、どう声をかければ良いか・・・もし本人が自殺してしまったら・・・ということも考えてしまいます。
どんな接し方をしても、どんなに最善を尽くしたとしても、愛する人がうつ病自殺で死んだら、支後者は自分を責めてしまいます。
当事者の自殺を防止できる可能性を高めると同時に、不幸にもそれができなかったとしても、周囲の人が「やれるだけの接し方はやった」と思えるような対策を推奨します。人事を尽くして天命を待つ、という方法です。
それは、うつ病患者さんだけでなく支援者も含めて、「マイナスをできるだけ少なくする」という発想です。その、もっとも大切なポイントが、「不調を察知したら(気がついたら)声をかける」という接し方です。
実は声をかけようが声をかけまいが、自殺されたら、後悔するのです。声をかけた場合は、声をかけたのに自分には話してくれなかった、それ以上は対処できなかった、と。
声をかけなかった場合は、なんとなくおかしいと思っていたのに、声をかけなかった...。
もともとどちらもマイナスなのです。だったら、声をかけた接し方のほうがいい。もしかしたら、あなたの声かけによって、当事者が助けを求める可能性があるからです。
実際は「何か変だな」と思っていても、周囲の人も日常生活の中に適当な理由を見つけて、「大したことはないんだ。しばらくすれば立ち直る。様子を見ておこう」と、結局何もしないことが多いのです。
とはいえ、これがなかなか難しい接し方なのです。むやみに声をかけるとかえって、うつ病患者さんの気持ちを逆なでするのではないか、とか自分が声をかけたことで、うつ病患者さんが自分を失い極端な行動に出たらどうしようなどと考えてしまいます。
いきなり心理的なテーマを話題にするのではなく、まず身体的なテーマに関する心配をきっかけに話を進めてほしいのです。
うつ病患者さんとの人間関係に自信がある場合はいきなり、「何か悩んでいることがあるのか」とか「○○のことで困っているのではないか」と切り出してもいいでしょう。
ところが表面飾りが強いうつ病患者さんの場合、どうしても心理面からのアプローチには壁をもうけてしまう傾向があります。
そこで、「最近顔色が良くないような気がするんだけれど、体調はどう」とか「何か疲れているような印象があるのだけど、ちゃんと食事とっている?」などのように体の調子を気遣う言葉から始め、体調管理をテーマにした話題をしばらく続けてみます。
そこから、相手が話し始める状態であれば、本人の苦しみについて耳を傾けます。もしそれ以上話が発展しない場合、「何かあったら相談に乗るからね」という「私はあなたのことを心配しているよ。力になるよ」というメッセージを残して、あっさりと会話を終えてください。
必死になって、それ以上聞き出すことは、かえってうつ病患者さんの心の壁を高くしてしまいます。おそらく、今のタイミングであなたに自分の心の苦しみをを説明することができなかったのです。
あなたに気を使って話しにくかったのか、うつ病の波がたまたま収まっていて、今日は相談しようと思わなかったのか、周りの環境から「ここでは相談できない」と思ったのかはわかりません。
うつ病の方への接し方
―心に寄り添うための声かけと姿勢―
うつ病の方にどう接すればいいのか。身近に苦しんでいる人がいるとき、多くの人が戸惑い、悩みます。
「励ましたいけど、何を言えばいいのか分からない」
「どう声をかけても反応がなくて、余計に距離を感じてしまう」
そんな気持ちを抱くのは自然なことです。
うつ病は、単なる「気持ちの問題」や「怠け」ではありません。脳の働きや神経伝達のバランスが崩れ、エネルギーが極端に落ちた状態です。ですから、本人が「頑張ろう」と思っても、身体も心も動いてくれないのです。
まず、その事実を理解することが、最初の「寄り添い」です。
1. 「励ます」より「認める」ことを大切に
多くの人が最初にしてしまいがちなのが、「励ましの言葉」です。
たとえば、
-
「元気出して」
-
「大丈夫だよ」
-
「もっと外に出てみたら?」
これらは一見、優しい言葉ですが、うつ病の人には"責められているように"聞こえてしまうことがあります。
なぜなら、本人も「元気を出したい」「外に出たい」と思っているのに、それができない自分をすでに責めているからです。
そのため、「頑張って」「元気出して」よりも、次のような言葉が心に届きやすいです。
-
「無理しなくていいよ」
-
「今日はここまでできただけでもすごいね」
-
「つらい中でも話してくれてありがとう」
たとえ小さなことでも、"できたこと"や"感じたこと"を認めてあげることが、心を支える力になります。
2. 「沈黙」も、安心できる空気のひとつ
うつ病の方は、会話すること自体がつらいと感じることがあります。だから、無理に話題を作らなくても構いません。
一緒に静かに過ごす時間も、立派な「支え」になります。
たとえば、
-
隣でお茶を飲むだけ
-
同じ部屋で本を読む
-
テレビをつけておくけれど、お互いに言葉を交わさない
そうした何気ない「沈黙の共有」が、本人にとって「安心していられる場所」になるのです。
沈黙を怖がらず、「ここにいていい」と感じられる雰囲気を作ることが大切です。
3. 「質問攻め」ではなく、「見守る姿勢」
よかれと思って、「どうしたの?」「なぜそんな気持ちになるの?」と理由を聞きたくなることがあります。
ですが、うつ病のときは自分の感情や思考を整理する力が弱まっているため、説明すること自体が負担になることがあります。
代わりに、こんな言葉が効果的です。
-
「話したくなったら、いつでも聞くよ」
-
「今は言葉にならなくても大丈夫」
-
「無理に話さなくてもいいよ」
このような「見守る言葉」は、相手に"安心して沈黙できる権利"を与えます。人は「話してもいい」「話さなくてもいい」と感じたとき、少しずつ心を開けるようになります。
4. 「解決しよう」としない勇気
多くの人は、誰かが苦しんでいると、「どうにかして助けたい」と思います。ですが、うつ病のときに必要なのは、"解決策"ではなく"共感"です。
たとえば、本人が「もう何もかもダメだ」と言ったときに、「そんなことないよ」「頑張れば良くなるよ」と言ってしまうと、本人は「自分のつらさを分かってもらえなかった」と感じてしまうことがあります。
そんなときは、答えを出そうとせず、ただ「その気持ちを受け取る」ことが大切です。
-
「そう感じるほど、つらかったんだね」
-
「本当に頑張ってきたんだね」
-
「今は苦しいよね。そばにいるからね」
"正しい言葉"ではなく、"気持ちを分かろうとする姿勢"が、心に届きます。
5. 「回復の波」を理解して、焦らない
うつ病の回復は、「階段」ではなく「波」のように上下します。少し元気になったと思ったら、また落ち込む。それを見て、「せっかく良くなったのに」「また戻っちゃった」と思うかもしれません。
けれど、それは後退ではなく、「波の中の回復プロセス」です。調子の良い日と悪い日を行き来しながら、少しずつ回復していきます。
そのため、周囲は「良くなった/悪くなった」と一喜一憂せず、長い目で見守ることが大切です。
-
「今日はゆっくり過ごせばいいね」
-
「昨日より少し笑顔が見られて嬉しいよ」
そんなふうに、"今この瞬間"の気持ちを受け止めていくことが、本人の安心につながります。
6. 支える人自身も、無理をしないで
うつ病の方を支えるのは、とてもエネルギーのいることです。「支えなければ」と気を張り続けてしまうと、支える側まで疲れきってしまうことがあります。
だからこそ、支える人自身も「休む」ことが大切です。
-
1人の時間を取る
-
信頼できる人に話す
-
専門家(カウンセラーなど)に相談する
「自分の心を守ること」も、相手を支えるための大事な行動です。支える人が笑顔でいられることが、うつ病の方にとっても安心の源になります。
7. 専門的なサポートを尊重する
うつ病は、医師や心理士などの専門家の治療・支援によって回復が進みます。身近な人ができるのは、その治療を支える"土台"を作ることです。
たとえば、
-
通院や薬の管理をそっと手伝う
-
医師の指示を尊重する
-
「治療を続けてえらいね」と声をかける
といったことが、本人の"治そうという力"を支えます。
逆に、「薬に頼りすぎじゃない?」「病院に行かなくても平気じゃない?」といった言葉は、治療への信頼を揺るがせてしまうことがあります。
専門的な治療と、身近な人の支え。その両方があってこそ、回復への道が開かれます。
8. 「あなたがいてくれてよかった」と伝える
最後に、何よりも大切なのは「存在を肯定する言葉」です。
うつ病の方は、自分を「価値のない人間」と感じてしまうことがあります。
そんなときに必要なのは、「あなたの存在が大切だ」と伝えることです。
-
「あなたがいるだけで安心する」
-
「あなたがここにいることが嬉しい」
-
「いてくれてありがとう」
この言葉は、回復のきっかけになることがあります。うつ病は"孤独との戦い"でもあります。
だからこそ、「あなたは一人じゃない」というメッセージを、言葉でも、態度でも、少しずつ伝えていくことが大切です。
まとめ
うつ病の方への接し方で最も大切なのは、「正しい言葉」ではなく「安心できる関係」です。
無理に励まさなくても、沈黙でも、ただそばにいてくれるだけで、救われることがあります。
そして、支える人自身も「完璧でなくていい」「できる範囲で大丈夫」と思ってください。
うつ病の回復には時間がかかりますが、ゆっくりとした時間の中で、「誰かが自分を理解しようとしてくれた」という記憶が、本人の心を支えていきます。
あなたの優しさは、きっと届いています。
たとえ今は反応がなくても、その温もりは静かに、確かに、心の奥で光っています。
うつ病を治し、再発も予防するためには、生きる目的を見出す必要があります。
多少の失敗でも落ち込むことはなくなります。
1. はじめに
うつ病は、単なる「気分の落ち込み」ではありません。脳の働きや神経伝達物質のバランスが乱れることによって、思考・感情・行動すべてに影響が及ぶ「病気」です。
そのため、本人の「気の持ちよう」ではどうにもならない状態にあります。周囲の人が適切に接することは、回復を支える大きな力になります。
逆に、悪気のない一言や無理解な態度が、本人を深く傷つけ、回復を妨げてしまうこともあります。
ここでは、「どう接するか」「何を話すか」「何を避けるべきか」を具体的に解説します。
2. うつ病の人の心の状態を理解する
うつ病の人は、自己否定の感情が非常に強く、「自分には価値がない」「迷惑をかけている」「何をしてもダメだ」という考えに支配されています。
また、思考力や判断力が低下しており、他人の言葉を「責められている」「否定されている」と過敏に感じてしまう傾向があります。
つまり、うつ病の人にとって世界は「自分を責める声」で満ちているように感じられるのです。
この状態を理解せずに「元気を出して」「もっと頑張って」と声をかけると、それは励ましではなく"追い打ち"になってしまいます。
3. 接し方の基本姿勢
(1)「治そう」としない
家族や友人はつい「なんとか元気にさせてあげたい」と思いがちですが、これは逆効果です。
うつ病は、本人の意志ではコントロールできない病気です。周囲が「治そう」とすると、本人は「治らない自分」にさらに罪悪感を抱いてしまいます。
まずは「治そうとしない」ことが大切です。その代わりに、「今のあなたのままでいい」「つらいね」と受け止める姿勢を持ちましょう。
(2)「否定せず」「評価しない」
うつ病の人は、常に自分を責めています。そのため、周囲からの小さな指摘や比較、アドバイスでも、「自分はダメだ」と感じてしまいます。
良かれと思って「そんなこと考えちゃダメ」「もっと前向きに」と言ってしまうのは禁句です。
大切なのは、「その気持ちをそのまま認める」こと。評価もジャッジもせず、「そう感じるんだね」と言葉を返すだけで安心感が生まれます。
(3)「沈黙を怖がらない」
うつ病の人は、会話する気力が湧かないことが多く、沈黙が続くことがあります。
その沈黙を「何か話さなきゃ」と埋めようとすると、本人を疲れさせてしまいます。
沈黙は「信頼の証」と捉えましょう。黙ってそばにいるだけでも、「自分を受け入れてくれている」という安心感を与えます。
4. 話し方の具体例
■ 望ましい言葉
-
「つらいね。話してくれてありがとう」
-
「無理しなくていいよ」
-
「あなたの気持ちは大事だよ」
-
「今日は少しでも楽に過ごせたらいいね」
-
「何かしてほしいことある?」
これらの言葉は、相手の感情を「受け止める」言葉です。アドバイスではなく共感を重視することで、相手の孤独感が和らぎます。
■ 避けたい言葉
-
「そんなことで落ち込むな」
-
「みんなも大変だよ」
-
「頑張れば何とかなるよ」
-
「考えすぎだよ」
-
「昔のあなたらしくないね」
これらの言葉は、相手を否定したり、責めたりする響きを持っています。
特に「頑張れ」は、うつ病の人にとって「もう頑張れないのに」という絶望の言葉になり得ます。
5. 家族・友人としてできるサポート
(1)日常生活のサポート
うつ病の人は、食事・睡眠・身支度といった基本的なことすら難しくなることがあります。
「手伝おうか?」とさりげなく声をかけたり、「一緒に食べよう」「ちょっと外の空気を吸おう」と提案するのは良いサポートです。
ただし、「やらせよう」とするのではなく、「一緒にやろう」という姿勢で関わるのがポイントです。
(2)医療への橋渡し
本人が治療を拒否することもありますが、病気を理解してもらうために「一緒に話を聞きに行こう」と提案してみましょう。
精神科や心療内科は"特別な場所"ではありません。風邪をひいたら内科に行くように、心が疲れたら心の専門家に相談することは自然なことです。
(3)サポートする側も限界を持つ
支える家族や友人も、常に明るく優しく接することは難しいものです。
疲れたときには一人で抱え込まず、カウンセラーや支援団体に相談しましょう。サポートする人が壊れてしまっては、支え合いの輪が崩れてしまいます。
6. 職場や周囲の人としての接し方
うつ病の人が職場にいる場合、特に「仕事の評価」と「人としての信頼」を分けて考えることが重要です。
うつ病によって一時的にパフォーマンスが落ちるのは自然なことです。
上司や同僚は、「今は無理しないで」「調子のいい日に少しずつやろう」といった柔軟な対応を心がけましょう。
また、仕事の話をするときには、「今後どうしたい?」よりも「今、どんなことがつらい?」と"現在の状態"を確認するようにします。未来の話は、回復が始まってからで十分です。
7. 回復期の接し方
症状が少し落ち着いてくると、「以前のように頑張れるのでは」と期待してしまいますが、回復には波があります。
良い日と悪い日が交互に訪れるのが普通であり、完全に安定するまでには時間がかかります。
焦らせず、「昨日より少し楽になったなら、それで十分」と伝えてください。
また、本人が「また落ち込んでしまった」と自分を責めるときは、「波があるのは当たり前」と伝え、自己否定をやわらげるようにしましょう。
8. まとめ
うつ病の人にとって、最も必要なのは「理解されること」と「否定されないこと」です。
専門的な知識や技術よりも、「そのままのあなたでいい」というメッセージが何よりの支えになります。
-
元気づけようとしない
-
沈黙を怖がらない
-
評価や助言より共感を
-
無理せず寄り添う
この4つを意識するだけで、相手は少しずつ安心を取り戻します。
うつ病は孤独な病気ですが、「一人ではない」と感じた瞬間から、回復への道が静かに始まるのです。
もしかしたら、うつの波の状態が変化しているかもしれません。声かけをしたときに、あなたのことを嫌がっているようであれば、あなたが「うつ病患者さん」にとっては苦手なのかもしれません。
あなたは支援したいという強い気持ちからかもしれませんが、それは販売員がしつこく商品を勧めているようなものなのです。今の「うつ病患者さん」は自分のペースで自分の好きなサービスを受け取りたいのです。
死にたいという気持ちを抱えている「うつ病患者さん」に対して、話を聞くという作業はどのような意味を持つのでしょうか。死にたいという気持ちを持つ人の特徴を考えてみましょう。
心身の疲労感があり、仕事や生活をうまく回せないようになります。
1、行き詰まっているのはどことなく「自分に責任があるのではないか(自分が怠けているだけ、能力が無いだけ)」と感じ、それを周囲に責められるのではないかという強い不安を持っています。
2、どうしてこうなったのか自分でも自分のことをよく理解できず、うまい話し方もできない。
3、自分の心や体をコントロールできず、今の状況を打開できない状態が続くと「自分は何もできない」という無力感を感じます。
みんなの中でこのように無力感を感じるのは自分だけであり、そんな自分はみんなから見捨てられるのではないかと恐れています。
このような「うつ病患者さん」は、初めのうちは誰かに助けを求めたかもしれません。ところが自分のことを正しく説明できないために、周囲の人も「気のせいだよ」とか「誰だって少しは悩むことがあるものさ」などと適当な接し方をされます。
あるいは、「考えすぎじゃないの。君のほうからみんなの中に飛び込んでみたら」などというアドバイスをもらいます。周囲の人も、「うつ病患者さん」を積極的に力づけようとして、さまざまな接し方をしてくれたでしょう。
でも、エネルギーが低くなっている「うつ病患者さん」は、「そういう状態ではないのだ」などとそれを否定することができず、我慢して聞くしかなかったのです。それは逆にエネルギーを消耗させる話し方になってしまうのです。
うつ病を治し、再発も予防するためには、生きる目的を見出す必要があります。
多少の失敗でも落ち込むことはなくなります。